・薬を買いに来たけど色んな種類がある・・・
・どの成分が何の症状に効くんだろう?
・どっちも咳に効くって書いてあるけど、どう違うんだろう?
体調が悪くて市販薬を買う際、種類が多すぎてどれを選んだらいいかわからなかった経験はありませんか?
私は薬剤師として10年以上病院に勤務し、主として医薬品情報の収集・評価を行ってきました。医薬品等について、根拠をもとに有効性や安全性の分析を日々行っています。
そこでこの記事では、病院でも近年用いられている、有効性・安全性・経済性を考慮した薬剤選択の方法をお伝えします。この考え方は医療業界で、「フォーミュラリー」と呼ばれています。
この記事を読めば、市販薬を選ぶ上で注目すべきポイントがわかります。
市販薬を選ぶ3つの基準、有効性・安全性・経済性の詳細について、これから解説していきます。
結論:臨床試験結果が大切

市販薬を選ぶ上で重要な判断材料は下記情報です。
有効性:臨床試験結果、臨床ガイドライン、内的妥当性・外的妥当性
安全性:臨床試験結果、特殊な患者集団での使用可否
経済性:1回または1日あたりの値段(有効性・安全性に差が少ない場合)
有効性・安全性・経済性のそれぞれについて、「医療用医薬品」の場合と「市販薬」の場合での違いを踏まえて解説します。
「有効性」の判断材料
医療用医薬品では

医療用医薬品の有効性は、
・臨床試験結果
・臨床ガイドライン
・試験結果の正しさ・他の人にもあてはまるか
上記の情報をもとに判断します。
臨床試験結果
臨床試験とは、新しい薬が本当に「安全で効果があるかどうか」を、人で確かめるための検査です。すでに動物などでの実験(前の段階)は終わっており、人に使う準備ができた段階で行われます。
医療用医薬品の有効性は、世の中に数多く存在する臨床試験論文を収集し、その内容を精査することで判断します。
臨床ガイドライン
臨床ガイドラインとは、病気の「診断」や「治療」をどう進めたらよいかについて、専門の医師たちが話し合い、科学的な根拠に基づいて作った「治療の道しるべ」です。
臨床ガイドラインは、世界各国で作成されています。海外では古くから使用されている薬でも、日本では発売してまもないことから情報が少ない場合があります。そのため、日本国内のガイドラインのみならず、海外のガイドラインも参考に有効性の評価を行います。
試験結果の正しさ・他の人にもあてはまるか
試験結果の正しさは、「この薬のおかげで良くなった」と自信をもって言えるかどうかで判断します。たとえば、他の要因(例:年齢やもともとの健康状態)が結果に影響していないかをよくチェックします。
他の人にもあてはまるかは、「この試験で効果があった薬は、ほかの病院や国の患者さんにも効果があるのか?」という視点で判断します。
たとえば、若い男性だけを対象にした試験で良い結果が出ても、高齢者や女性に当てはまるかはわかりません。
「試験結果の正しさ」「他の人にもあてはまるか」という基準は、専門用語でそれぞれ「内的妥当性」「外的妥当性」と呼ばれます。
市販薬では
市販薬の有効性も、医療用医薬品と同様の基準で判断します。
ただし、医療用医薬品と比べて市販薬は市場規模が小さいため、臨床試験の数も少なくなりがちです。医療用医薬品の場合よりも、結果に優劣をつけづらい場合が非常に多いです。
「安全性」の判断材料
医療用医薬品では

医療用医薬品の安全性は、
・臨床試験結果
・特殊な患者集団での使用可否
上記の情報をもとに判断します。
臨床試験結果
前述の通り、臨床試験とは、新しい薬が本当に「安全で効果があるかどうか」を、人で確かめるための検査です。有効性のみならず、安全性についても確認が行われています。
具体的には、副作用発現率、重篤な有害事象、長期使用時の安全性などの情報が集められています。
医療用医薬品の安全性も、臨床試験論文の収集・内容精査をすることで判断します。
特殊な患者集団での使用可否
特殊な患者集団とは、「一般的な患者とは違う特徴をもっていて、薬の効果・副作用が変わる可能性がある人たちのグループ」のことを言います。
具体的には、小児や高齢者、妊婦・授乳婦、肝臓・腎臓が弱っている人などを指します。
特殊な患者集団でも使用経験がある薬かどうかを、臨床試験や薬の説明書(添付文書といいます)を見て判断します。
市販薬では
市販薬の安全性も、医療用医薬品と同様の基準で判断します。
ただし前述の通り、医療用医薬品と比べて市販薬は市場規模が小さいため、臨床試験の数も少なくなりがちです。医療用医薬品の場合よりも、特殊な患者集団での使用経験がない場合が多いです。
「経済性」の判断材料

経済性については、有効性や安全性が同等、または差が軽微である場合に判断材料として使用します。
「有効性や安全性に大きな違いがある」場合には、より優れているものを選びます。この場合、経済性は薬を選ぶ判断材料にはなりません。
「有効性や安全性が同等である」場合には、「経済性(=値段が安い)」ものを選びます。得られるメリットが同じなら、より安価であるほうが、経済性に優れているといえます。
「有効性や安全性に小さな違いがある」場合には、その差が値段に見合うかを考えて選びます。効き目がわずかに高くても、他の薬より値段が10倍高いのであれば、それは値段に見合った効果があるとはいえません。
医療用医薬品では
基本的に薬の1回あたりの値段や1日あたりの値段を比較して判断します。他にも、治療全体にかかる医療費(例:副作用による追加治療費、入院期間の短縮など)も考慮する場合があります。
市販薬では
市販薬の経済性も、医療用医薬品と同様に1回(または1日)あたりの値段を比較して判断します。しかし、治療全体にかかる医療費は考慮しません。
市販薬の役割は、対症療法にあります。対症療法とは、病気の「原因」を治すのではなく、「症状(つらさ)」をやわらげる治療のことを言います。対症療法に対する使用のため、治療全体にかかる医療費は算出できず、よって考慮することもありません。
まとめ:有効性・安全性・経済性の判断材料

・「有効性」の判断材料
⇛臨床試験結果、臨床ガイドライン、試験結果の正しさ・他の人にもあてはまるか
・「安全性」の判断材料
⇛臨床試験結果、特殊な患者集団での使用可否
・「経済性」の判断材料
⇛有効性・安全性に差が少ない場合に考慮
市販薬を選ぶうえで注目すべきポイントは上記3つの基準です。
しかしながら、専門知識がなければ臨床試験結果などの正しい評価は困難です。
そこでこのブログでは、専門知識がなくても市販薬を選べるように、各薬効別の有効性・安全性・経済性の比較をわかりやすくお伝えしていきます。

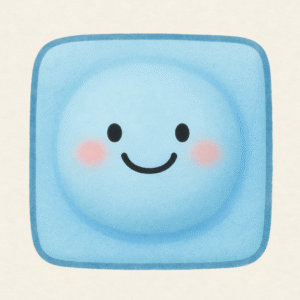


コメント